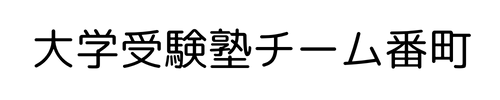『東大教師が新入生にすすめる本』の感想、書評
東大の先生による新入生のためのブックガイドとして、雑誌『UP』(東京大学出版会)に掲載されたアンケートを再構成した本です。
1.私の読書からー印象に残っている本
2.これだけは読んでおこうー研究者の立場から
3.私がすすめる東京大学出版会の本
という3問の設問で構成されます。
平成16年初版のもののまえがきは、ホリエモンこと堀江貴文さんのゼミの教官だった、船曳建夫先生が書かれています。船曳先生は、ベストセラー『知の技法』の編者としても有名です。
船曳先生は、まえがきを「大学1年生という一瞬」と題しています。生涯に一度しかない輝かしい一瞬。本書は、その大学新入生に対する祝福の言葉だそうです。まあ、そのような、ありがたいものと捉えることもできますし、厳しい洗礼と捉えることもできます(笑)。
全体的に、ご自分の専門分野の本が多く挙げられています。新入生に、今すぐ読め、ということなのか。今すすめるから後日読め、ということなのか。前者であれば、かなり厳しいものも多いです。本の難しさにも、色々あると思いますが、前提知識がないと理解できない類の本も多いだろうからです。大学受験数学に例えると、教科書レベルを理解していないと、教科書を超える、チャート式やFocus Goldを理解できませんね。そのようなことが、かなり起こりうるのではないかと。
一方で、塾長が教養課程の時に『物理科学』という授業の担当だった物理の教授が『日本人の英語』(岩波新書、マーク・ピーターセン)を挙げていて「諦めかけていた冠詞に再び挑戦しようかと思わせてくれる本」としています。東大教授も、英語の冠詞には苦労するのだなあと。『日本人の英語』は『続・日本人の英語』とともに、他の工学系の先生も挙げています。
また、天文学の先生が『法隆寺論』『柿本人麻呂論』『聖徳太子』といった本を挙げていることがあります。不完全な史料から史実を推定する作業は、観測で得られる不完全な少ない情報から天体で何が起こっているかを推定する作業に似ていて、参考になるそうです。東大教授の研究領域にまで達すると、いかなる分野でも、通づるものがあるのだなあ、と思いました。
三たび物理の先生ですが、『戦争と平和』(トルストイ)、『罪と罰』(ドストエフスキー)を挙げている先生もいます。『戦争と平和』は、複数の物理の先生が挙げています。ある先生は、「要は、ある目的を離れて思考することであ」る、とおっしゃっています。よくわかりませんね(笑)。
塾長は、司馬遼太郎さんが好きです。ある図学の先生は『竜馬がゆく』(文春文庫)を挙げています。
小説は、全体として、ドストエフスキー、夏目漱石が挙げられることが多いです。
2004~2008年版は、急に、『ファインマン物理学』を含め、ファインマン先生の著作が増えるような気がします。
興味がある人、将来の専攻に考えている人は、ここで挙げられているような本を、早くから手にとってみてはいかがでしょうか。
『東大教師が新入生にすすめる本』とフーコー
権力と知の関係性の観点からすれば、大学教授による新入生への本の推薦は、単なる知識の伝達ではなく、権力関係の再生産として捉えることができます。教授は、大学という制度的権威を背景に、特定の知識やテクストを「読むべきもの」として提示することで、新入生の知的な関心や思考の方向性を規定しようとしているのです。
また、言説分析(言葉や文章がどのように社会を形作っているのかを分析する考え方)の観点からは、推薦される本のリストそのものが、一つの言説的実践として機能していると言えます。そのリストは、東京大学というエリート教育機関が重視する知識体系や価値観を体現しており、新入生に特定の「真理」を内面化(外から与えられる情報や価値観を、自分の内面に取り込み、自分のものにしていくこと)させる働きを持っています。推薦図書リストは、大学教育という規律訓練の一環として、新入生を特定の知的規範に適合させるための装置なのです。
さらに、主体の構築という視点から見れば、推薦図書を読むことは、新入生が「東大生」としての主体性を形成する過程の一部だと言えるでしょう。推薦された本を読み、理解することは、大学の知的共同体への参入を意味します。新入生は、推薦図書を通して、東大生としての自己認識を獲得し、エリートの一員としてのアイデンティティを構築していくのです。
ただし、フーコーの権力論からすれば、この過程は、新入生が受動的に権力に従属することを意味するわけではありません。新入生は、推薦図書を批判的に読み、自らの解釈を生み出すことで、支配的な言説に抵抗し、オルタナティブな知の可能性を切り拓くこともできるはずです。大学教育の中で、既存の知の枠組みを問い直し、新たな思考を生み出すことは、フーコーが重視した「批判」の実践だと言えるでしょう。
また、推薦図書をめぐる言説は、東京大学という特定の制度的文脈の中で生み出されたものです。他の大学や教育機関では、異なる推薦図書リストが存在し、別の知的規範が重視されているかもしれません。フーコーの視点からすれば、これらの差異は、知の多様性と権力関係の複数性を示唆するものだと言えます。私たちは、特定の推薦図書リストを絶対視するのではなく、複数の知的伝統や価値観の並存を認め、それらの間の対話と交渉を促進していく必要があるでしょう。
東京大学の先生達が新入生に本を推薦することは、知識の伝達であると同時に、権力関係の再生産でもあります。それは、大学教育という規律訓練の一環であり、新入生を特定の知的規範に適合させる働きを持っています。しかし、新入生は、推薦図書を批判的に読み、オルタナティブな知の可能性を探ることで、支配的な言説に抵抗することもできるはずです。
フーコーの思想は、推薦図書をめぐる言説の背後にある権力の作用を可視化し、知の多様性と複数性を認めることの重要性を示唆しています。私たちは、特定の推薦図書リストに囚われることなく、多様な知的伝統との出会いと対話を通して、新たな思考の地平を切り拓いていかなければならないのです。大学教育の目的は、既存の知を再生産することではなく、批判的な思考力を培い、知の創造に参与する主体を育むことにあるのかもしれません。
『東大教師が新入生にすすめる本』とハイデガー
ハイデガーにとって、大学とは単に専門的な知識を教授する場ではなく、学問の本質を問い、真理を探究する場でした。彼は『ドイツ大学の自己主張』の中で、大学の使命について次のように述べています。「大学の本質的な課題は、学問的認識を通じて、現存在全体を最高度の明晰性と責任とへともたらすことである」。つまり、大学教育の目的は、学生たちが自らの存在の意味を問い直し、本来的に生きることを促すことなのです。
この観点から見るなら、先生達が新入生に本を勧めるという行為は、単なる読書案内ではなく、学問の世界への招きだと言えるでしょう。彼らは自身の研究や思索を通じて得た洞察を、本という形で学生たちに伝えようとしているのです。そこには、若い魂を導き、新たな地平を切り拓こうとする教育者の情熱が込められているはずです。
ハイデガーはまた、学問を「現存在の根本様式」の一つと捉えました。学問とは、事象そのものに向き合い、その本質を問うことです。これは容易なことではありません。なぜなら、私たちは日常的な見方や先入観に囚われがちだからです。しかし、本を読むという行為は、そうした殻を破り、新たな視点を獲得する契機となり得ます。先生達が勧める本には、既成の枠組みを超えて、世界を根源的に捉え直す力が秘められているのです。
もちろん、ここで重要なのは、単に本を読むことではなく、本と真摯に対話することです。ハイデガーが強調したように、言葉とは単なる記号ではなく、存在を開示する出来事です。私たちが本を読むとき、そこには著者との出会いがあります。著者の思索に耳を傾け、みずからの存在を問い直すことで、私たちは新たな地平を切り拓いていくことができるのです。
また、先生達が新入生に本を勧めるという行為には、学問共同体の一員として迎え入れるという意味合いもあるでしょう。ハイデガーは、大学を「指導者と追随者の共同体」と呼びました。そこでは、先生と学生が共に真理を探究し、互いに切磋琢磨しながら成長していきます。新入生に本を勧めることは、彼らを学問の世界へと誘い、共に歩むことを呼びかける象徴的な行為なのです。
ただし、ここで注意しなければならないのは、本を読むことが自己目的化してはならないということです。ハイデガーが批判したように、大学が単なる専門知識の習得の場に堕してしまっては、その本来の使命を見失ってしまいます。あくまでも大切なのは、本を通じて獲得した知見を、自分自身の生の課題として引き受けることなのです。
そのためにも、先生達は学生たちに対して、本を批判的に読む姿勢を促す必要があるでしょう。ただ受動的に著者の意見を受け入れるのではなく、みずからの経験や思索と突き合わせながら、本と対話することが求められます。そうした能動的な読書こそが、学生たちを本来的な在り方へと導く鍵となるはずです。
さらに言えば、先生達自身も、常に学び続ける姿勢を持つことが大切です。学問の道に終わりはありません。私たちは誰もが、みずからの無知に気づき、新たな知を求めて歩み続けなければならないのです。先生達が学生たちに示すべきは、完成された知識ではなく、真理を愛し、探究し続ける生き方なのかもしれません。
東京大学の先生達が新入生に本を勧めるという一見些細な行為は、実はハイデガーの思想と深く響き合っています。それは単なる知識の伝達ではなく、学問の本質を問い、本来的な在り方を模索する契機なのです。先生達の推薦図書リストには、学生たちを導こうとする情熱と、共に真理を探究する友愛の精神が込められているはずです。
新入生たちには、そうした先達からのメッセージを謙虚に受け止め、みずからの人生を問い直すことが求められます。本を媒介として、先生達との、そして先人達との対話を重ねることで、彼らは新たな地平を切り拓いていくことができるでしょう。そのとき、大学は単なる学舎ではなく、真理への愛に溢れた生きた共同体として、学生たちの魂を育んでいくはずです。
『東大教師が新入生にすすめる本』とデリダ
まず、「東京大学の先生」という主体は、一枚岩ではありません。各教員は、それぞれ異なる専門分野、思想的立場、価値観を持っており、その多様性は「何冊か本を勧める」という行為にも反映されているはずです。しかし、「東京大学の先生」という集合的なアイデンティティが前面に押し出されることで、その多様性は覆い隠されてしまいます。ここには、ある種の権力の作用が見て取れるでしょう。
また、「東京大学の新入生」という存在も、脱構築の対象となり得ます。新入生は、入学試験という制度的な選抜を経て、「東大生」というアイデンティティを付与されます。しかし、それは単なるラベルに過ぎず、新入生一人一人の個別性を捨象したものだと言えます。「東大生」という主体は、大学という制度によって構築された仮構であり、決して自明の存在ではないのです。
さらに、「本を勧める」という行為自体も、脱構築の対象となります。本を勧めるということは、ある特定の知識やイデオロギーを推奨し、他の知識やイデオロギーを排除することでもあります。そこには、大学という権威による言説の統制が働いていると考えられます。デリダが指摘したように、テクストの意味は決して一義的に確定できるものではありません。しかし、本を勧めるという行為は、テクストの多義性を抑圧し、特定の読解を強要するものでもあるのです。
ただし、だからと言って、本を勧めること自体が全く意味を持たないわけではありません。デリダは、「pharmakon(ファルマコン)」という概念を提示しました。「pharmakon」とは、毒にも薬にもなり得る両義的なものを指します。本を勧めるという行為も、知的な啓発の契機となる一方で、特定のイデオロギーを注入する装置にもなり得るのです。
重要なのは、この両義性を認識し、批判的に吟味することでしょう。東京大学の先生達が本を勧めるとき、彼らは自らの権力を行使しています。しかし、その権力は絶対的なものではなく、常に脱構築の対象となり得るのです。新入生は、勧められた本を無批判に受け入れるのではなく、そこに潜む権力関係を見抜き、自らの読解を通してテクストの多義性を開いていく必要があります。
そのとき、「東京大学の先生」と「東京大学の新入生」という主体もまた、脱構築されていくことになるでしょう。本を媒介とした対話の中で、両者の境界は揺らぎ、固定された関係性は解体されていきます。そこに生まれるのは、知の伝達ではなく、知の生成のプロセスです。
「東京大学の先生達が、東京大学の新入生に、何冊か本を勧める」という行為は、決して一枚岩の権威から無知の学生への一方的な贈与ではありません。それは、権力と知のダイナミックな相互作用の場であり、脱構築の契機を孕んだ出来事なのです。重要なのは、その複雑さと両義性を認識し、批判的に吟味していくことでしょう。そのとき、大学という制度もまた、絶えざる脱構築のプロセスの中で更新されていくのではないでしょうか。
キムタツの東大に入る子が実践する勉強の真実(KADOKAWA)
この記事を書いた人
大学受験塾チーム番町代表。東大卒。
指導した塾生の進学先は、東大、京大、国立医学部など。
指導した塾生の大学卒業後の進路は、医師、国家公務員総合職(キャリア官僚)、研究者など。学会(日本解剖学会、セラミックス協会など)でアカデミックな賞を受賞した人も複数おります。
40人クラスの33位での入塾から、東大模試全国14位になった塾生もいました。